製法と原料による塩の分類
「あらしお」の話
(2010記載)
「フレーク塩」の話
(2010記載)
「焼塩」の話
(2010記載)
「藻塩」の話
「自然塩」の話
(2010記載)
「ミネラル塩」の話
(2010記載)
「化学塩」の話
(2010記載)
市販の塩の種類
「あらしお」の話
(旧原稿)
自然塩の話
(旧原稿)
岩塩の話
天日塩の話
生活用塩とは
深層海水塩
塩の添加物 |
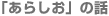
 |
 |
「あらしお」には、荒塩と粗塩の2種の漢字があります。あまり厳密に使われていないようですが、商品で「・・のあらしお」という表現をしているのは、フレーク塩でガサガサのかさばった塩で「荒塩」をいっているようであり、「粗塩」と表現しているのは苦汁分が多い凝集晶塩をいっているようです。
フレーク塩(「あらしお」「荒塩」)は濃い塩水を平釜で静かに熱して表面に出てくる薄いピラミッド型のトレミー結晶が脱水、包装の過程で結晶が壊れてできる、平板状の非常にかさばった塩をいう。結晶がきれいで、付着性がよく、溶解が速い。通常苦汁混じりの湿った塩で販売されているケースが多いが、乾燥したフレーク塩もある。かさ比重は約0.7g/cm3で、量産した立方晶に比較し2倍近くになる。生産性を上げるために温度を上げたり、撹拌すると凝集型結晶が混じる。一般にはある程度凝集晶も混ざる。昔は和風料理では珍重された。例えば、京料理で珍重された「あく引き塩」は昔のレベルでは純度のよいフレーク塩で、現在のフレーク塩がほぼ同じと考えてよい。
粗塩(あらしお)は従来は苦汁分が多い粗悪塩の呼称で真塩(ましお)と対比される言葉であったが、最近は苦汁添加塩を粗塩といっている傾向があり、悪いイメージはなくなっている。結晶は一般に微粉砕した天日塩か、平釜凝集晶が多いようである。どの程度苦汁があれば粗塩かという定めはなく、各社が都合がよいように商品宣伝に使っているのが現状だろう。 |
|
|
|
|
|
|
 |