製法と原料による塩の分類
「あらしお」の話
(2010記載)
「フレーク塩」の話
(2010記載)
「焼塩」の話
(2010記載)
「藻塩」の話
「自然塩」の話
(2010記載)
「ミネラル塩」の話
(2010記載)
「化学塩」の話
(2010記載)
市販の塩の種類
「あらしお」の話
(旧原稿)
自然塩の話
(旧原稿)
岩塩の話
天日塩の話
生活用塩とは
深層海水塩
塩の添加物 |
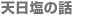
 |
 |
 |
天日塩は海水を塩田に導き太陽と風の力で蒸発させて塩の結晶を取る。日本のかっての塩田は釜で焚いて結晶を取っており天日塩ではありません。日本で輸入される塩はほとんど天日塩が輸入されています(塩の需給を参照)。輸入の大部分はメキシコゲレロネグロ塩田と西オーストラリアの4カ所の大規模塩田です。100トン以下の小規模の商品輸入として中国、インドネシア、フランス、イタリー、東オーストラリアなど各地から輸入されています。
天日塩の作り方も品質は砂漠地帯と雨の多い地域では異なっています。メキシコ、西オーストラリア、地中海の一部などのほとんど雨がない砂漠地帯の大塩田では、結晶池の底部は厚い塩の層でできています。長期間露天で蒸発させるので砂塵が混ざりますが、底土からの泥の汚染は比較的少なく、大きな硬い結晶になります。雨が多い地域、雨期がある地域の塩田は、塩の層を作れないし、降雨時の管理のために塩田区画が小さくなります。そのため底土がむき出しになり、かん水が泥水になったり、採塩の時に塩田地盤や側壁の泥が入り汚れてきます。その対策として中国などで側壁を煉瓦にしたり、底部にタイルをしくなどの工夫をしていますが、不完全なケースが多いようです。降雨が多い地域の塩田、小規模の塩田ではどうしても泥などの混入が多く衛生上問題があるところが多いのが実状です。砂漠型の天日塩は溶けにくく、雨期のある天日塩はやや溶けやすい塩になります。
日本に輸入された天日塩は、塩事業センターから原塩、粉砕塩として販売されています。ソーダ工業用以外では、道路融雪、食品の粗加工、工業用、加工塩の原料などの用途が多いようです。先進国では天日塩をそのまま食用とする例は少なく、溶解してせんごう(真空蒸発缶で再結晶)して精製塩とするか、徹底して洗浄して食用としています。日本では最近天日塩そのものを小口で輸入して家庭用に小袋で販売するケースも多く、泥などが混入している場合がありますが、むしろ自然でよいという宣伝もされているようです。
天日塩にはもう一つ心配なことは細菌類です。海洋の汚染をそのまま製品に持ち込むため、汚染成分がそのままはいるという問題もありますし、細菌類もくっついたままになっています。この点は「塩と細菌の話」を見て下さい。
天日塩=自然塩というイメージを持っている方もいますが、天日塩は自然エネルギーを使って濃縮している点で自然塩ですが、成分の面から見ると泥などの混入が多く、使い勝手もよいものとはいえません。しかし、石油や石炭を使う量が少なく、地球環境という視点で考えると環境に優しいといえると思います。
天日塩のことを岩塩という人が多いようです。岩塩と天日塩は違います。日本で流通している塩は岩塩はほとんどなく、大粒の不定形に破砕された塩は天日塩です。 |
 |
|
|
 |