塩味の常識
(2010記載)
塩のソムリエに
チャレンジ(2010記載)
高価な塩が
よい塩ではない
安全な塩を簡単に
見分ける方法
塩味の特徴
塩の上手な選び方
ユーザーのための
塩学入門
塩の賞味期限
漬物に使う塩
駐車場の凍結防止
|
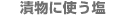
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
漬け物にはどんな塩がよいか。
カリウム入りの塩を漬物用にすすめられたが本当によいのでしょうか。 |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
漬け物の中の塩が少なくなりました。サラダ風に食べられる浅漬けが多く、昔の塩分の多い古漬けは店でもほとんど見かけません。梅干しですら昔の18%位から10%梅漬け全盛です。白菜などは5%位から3%以下になっています。減塩推奨のせいか、嗜好の変化のせいか、よく分かりません。今は冷蔵保管、ソルビン酸などの保存料添加、アルコール添加などが普通になっています。もし健康を気にしての減塩なら、あまり気にせずおいしいものを食べるのがよいと思うのですが。
| 1)漬け液のあがりが早いこと |
| 2)野菜など素材が軟化しないこと |
| 3)漬け上がりの味が慣れていること |
の要素が大切です。そのためには、漬け物に使う塩は、材料とのなじみが一番です。
材料とのなじみの良さでは漬け方が非常に大切です。材料が隙間なくきちんと並べられてないと水の上がりが極端に悪くなります。塩が樽の底に沈んでいるようだと、漬け液の上がりどころか、軟化したり腐ったりしてしまう。梅、大根、胡瓜などは特に注意が必要です。塩が全体に平等に行き渡らせることが大切になりますが、そのためには材料にくっつきやすい塩を選ぶのがポイントです。業務用ならば粉砕塩や白塩などの粗い粒より、並塩のように細かい塩がよいようです。微粒塩や「あらしお」ならさらになじみはよくなりますが値段が少し高くなります。天日塩ではしばしば泥が混入しています。漬物は直接口に入れるものですから、並塩、あらしおなどのせんごう塩がよいでしょう。
家庭用なら食塩がお徳用だが、乾燥しているからなじみが悪い。水を振ってかなり湿らせて使うとよいでしょう。使いやすいのは漬け物用として販売されている塩、苦汁添加塩などはさらに使いやすくなりますが、値段は倍以上になります。漬け物用塩はクエン酸、うまみ添加物などが入っており、保存性もうまみも向上します。苦汁が入った塩を使うと材料とのなじみは良く、底に沈んだりする失敗は少なくなりますが、漬け上がりの味が良くなるということは特にないようです。全体に塩がまんべんなく行き渡れば食塩や並塩に比較して漬け液の上がりがよくなるということもありません。
なお、上手に塩水の差し水をすること、焼酎などを少量加えるのも非常に有効になります。家庭用では一掴みの感じで塩の量を決めることが多いので、慣れた塩を使うのが一番でしょう。一掴みで塩の量を決めると、「あらしお」ではかなり塩が少なくなりますから、塩不足に注意してください。塩を変えたときは秤で計って使うことをおすすめします。
カリウム入りの塩を使った場合の質問がありましたが、私の経験では20%以上の塩化カリウムがあると味が変になります。10%程度ではなかなか分からないような差ですが、魚系では味が良くなるという人と、肉質が柔らかくなるという人がいるようです。好みの問題もありますからやってみないと分からないというのが私の意見です。 |
 |
|
|
 |